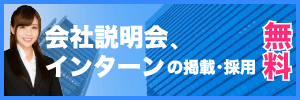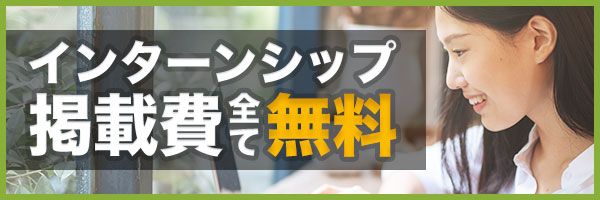就活で企業と学生の採用後ミスマッチをなくすには?
せっかく長い時間とコスト・手間をかけて採用した新入社員にも関わらず、「自分には合わない」とすぐに早期退職をしてしまう新入社員がいると企業にとっては大きな損失となります。逆に企業側からも、面接では優秀な人材だと思っていたのに採用後に実はそうでもなかったと感じることもあります。双方にとって不幸な採用活動のミスマッチは就職活動の過程で防ぐことができるのでしょうか。その方法を解説します。

- ・最も確実なのはインターンシップで実際に働いてもらうこと
- ├互いに実務に近い状況で「予行練習」ができる
- └互いにジャッジができる
- ・面接でミスマッチをなくす質問
- ├「想定内の質問」ではなく、その学生の人となりに迫った質問を
- └将来の夢や働き方の希望を聞いてみる
- ・面接や説明会で学生のギャップをなくす工夫
- ├実際の業務のフローや、最初の数年間の流れを説明
- └人事担当者だけでなく実務担当者が面接をする
- ・最後に
最も確実なのはインターンシップで実際に働いてもらうこと
最も確実にその人材が自社で働く上で能力を発揮できるかどうかを確認し、また学生にとってもギャップをなくすことができるのは「インターンシップ」を実施し、実際に働いてもらうことです。双方にとってリスクのない「お試し期間」としても有効で、互いに実際の業務を踏まえて見極めることができます。
互いに実務に近い状況で「予行練習」ができる
自社の実務に近い状況で学生にとっては「予行演習」としての業務を行ってもらうことで、イメージがわくと同時に入社後に互いに「こんなはずではなかった!」とショックを受けることもなくなります。新入社員が突然辞めてしまう可能性も限りなく抑えることができますし、企業側も一旦採用した新入社員を持て余してしまうこともなくなります。
互いにジャッジができる
面接でいくら「学生時代に頑張ったこと」のエピソードを聞いたところで、自社の業務でその「頑張った」能力を活かすことができるかどうかはわかりません。実際の実務に近い業務を行う学生を見て企業側は「想像以上に能力が高い!」「自分で言うほどには能力が高くない」などのジャッジを下すことができます。
もちろん学生側も「思っていたよりも自分にはこの業務は向いていないかもしれない」「会社の雰囲気が居心地がいいので、働いてみたい!」など会社への具体的なイメージを持つことで入社後のギャップを減らすことができます。
面接でミスマッチをなくす質問
とはいえ、インターンシップをすることができない、現実的ではない企業もあるでしょう。そんな場合には面接の質問で可能な限り双方のミスマッチをなくす内容を聞いておくことが重要となります。
「想定内の質問」ではなく、その学生の人となりに迫った質問を
最近の学生は多くの場合インターネットや「就活本」などの「マニュアル」をしっかりと読み込んで面接に臨んでいます。そのため、「想定内の質問」では決まった型どおりの優等生的な回答しか得ることができず、その学生の能力や考え方を知ることができないことも多くあります。
そのため、「想定外の質問」をすることで特に緊急時やトラブル時にどうするか、また普段の素の姿について知れる質問をすることでその学生の本当の姿や考え方、とっさのときに見せる「ストレス耐性」などを垣間見ることができます。
将来の夢や働き方の希望を聞いてみる
企業としては、採用するからには当然自社のために一生懸命働いてほしい!と思うかもしれませんが、人により理想とする働き方は異なります。がっつり仕事に生きたいタイプか、定時で趣味を楽しみたいのかなど、それぞれ人生設計があるはずです。そこで「将来は弊社の社長になりたいと思いますか?」「人生100年時代と言われますが、10年ごとにどのように生きていたいかライフプランを教えてください」といった質問をすることで、自分の人生の中で働くことがどのような位置づけとなっているのかを確認することができます。
自社の採用コンセプトの中で、たとえば「海外勤務もできる人材」「仕事にガッツリと没頭できる人材」が欲しいという場合には、「ワークライフバランス重視型」の学生は合わないですし、逆にクリエイティブ系の職種など「プライベートを充実させることにより仕事にも良い影響をもたらす」ような職種の場合には「趣味も大切にしながら働いていきたいです」といった人材の方が良いアイディアを豊富に持っている人材となる可能性が高いでしょう。
面接や説明会で学生のギャップをなくす工夫
次に、学生側のギャップをなくすための方法を見ていきましょう。
実際の業務のフローや、最初の数年間の流れを説明
学生にとっては、社会人として会社で仕事をするということ自体が未知なるものです。そのため、限られた会社のホームページやパンフレット、説明会だけでは全てを把握することはできません。そのため、入社後にギャップがあるのは当たり前ではありますが、できるだけそのギャップを減らすことが大切です。
たとえば、実際の業務フローを1日のスケジュールで見せてイメージしてもらったり、最初の数年間はどのような部署でどのような仕事をすることが多いのかなどを説明することで想像しやすくなります。「最初の2年間は店舗勤務で現場を体験してもらい、その後現場経験を活かして本社で商品開発などの勤務をすることになります」など説明しておけば、入社後に「店舗勤務なんてバイトのすることだ!」と途中で退職することもないはずです。
人事担当者だけでなく実務担当者が面接をする
また、面接時に実務担当者が面接をすることで、実際にどんな働き方をしているのか学生が聞けるだけでなく、実務担当者から見て「この学生は実務に向いている」「すぐ辞めそう」などの判断もできることがあります。実務担当者が面接をすることが可能であれば、1次~2次面接で人事と2名で面接を行なってみましょう。
最後に
企業と学生の採用後ミスマッチを100%なくすことはできません。しかし、ご紹介したような内容を就活の過程で行うことで、限りなく低くすることは可能です。双方にとって採用後ミスマッチは不幸でしかありません。可能な限りの手を尽くすことでミスマッチを減らしていきましょう。
母集団形成におすすめ

インターンや会社説明会の求人を無料掲載できる
- 導入企業1,500社 学生10万人以上の実績がある急成長メディア
- 3人に1人は東大、早慶、8割がGMARCH以上クラスと優秀な学生がほとんど
- メルマガやオファー送付など個別の集客プランも対応可能
おすすめの記事一覧

scoutコラム表示テストです~
続きを読む
てすと
続きを読む
てすとコラム 企業向け
続きを読む
テストコラム 企業向け
続きを読む
タグ追加テスト
続きを読む