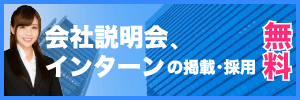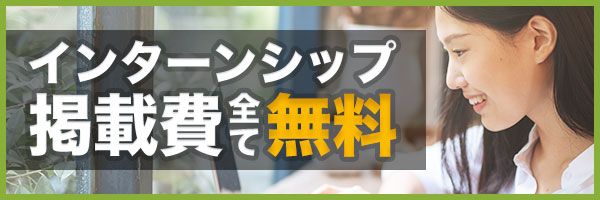売り手市場で要注意!内定辞退を減らすコツ
「売り手市場」と言われて久しいここ数年の新卒採用市場。どの会社も採用したいと思わせる優秀な学生は、複数社の内定を獲得したあとに比較検討し、入社する会社を決めるケースが増えています。企業側も、優秀な学生を確保し、採用充足するために内定辞退を防止する対策が重要となってきました。
では、内定辞退を減らすポイントはどこに隠されているのでしょうか?本来であれば、会社説明会から選考会、面接、内定通知、内定後までの一貫した流れを通して、会社理解が進み志望度が上がっていくように選考フローを設計することが重要ですが、ここでは、内定通知後の学生のフォローのポイントについて紹介します。

- ・学生のホンネを理解していますか?
- ・辞退リスクのある学生の特徴と内定後のフォローのポイント
- ├すぐに内定承諾した学生
- ├OBOGネットワークの強い部活・サークルに所属している学生
- ├親の影響を受けやすい学生
- ├併願している企業の中に、採用力の高い会社がある学生
- └承諾せずに長期間返答を保留している学生
- ・最後に
学生のホンネを理解していますか?
内定辞退を減らせるかどうかは、「採用担当者がどれだけ学生のホンネをヒアリングできているか」にかかっています。なぜなら、学生が内定の承諾を迷っているときに、ホンネを理解できていれば、その学生が必要とする情報の提供ができたり、話が合いそうな社員に会ってもらったりといった、有効な対応ができるからです。
学生が悩んでいるポイントと的外れの情報を提供してしまったり、ひたすら自社の魅力をアピールするようなことをしてしまえば、「この会社は自分を理解していないんじゃないか」という不安や不信感から、志望度は下がっていくでしょう。
しかしこの「ホンネ」、採用担当者にはなかなか話してくれない学生が多いのです。
なぜでしょうか?人は誰でも、自分を良く見せたり、相手を傷付けないように、時にはホンネを隠して会話をするものです。
例えば、
「本当は親に反対されたので辞退したいが、今までお世話になった人事の方にそんな理由で断るのは申し訳ないので、納得してもらえる理由にしなきゃ。」
「実は面接で話した社員と自分のタイプが合わなそうだったので辞退したいが、内定承諾しようと思っている会社は同業他社なので、できるだけ穏便に辞退しておきたい。」
「職種は同じで他社のほうが条件が良かったから他社に入社したいが、内定をもらうまでに熱い思いを語っているので、今更そんなこと言うのもかっこ悪い。」
といった感情から、ホンネを話さない学生はよくいます。
「学生が話していることは本当にそう思っていることなのか?」常に気にかけながらコミュニケーションをするよう、心がけましょう。
辞退リスクのある学生の特徴と内定後のフォローのポイント
「内定承諾をした学生から、突然辞退の連絡が来た」という経験、多くの採用担当者がしたことあるのではないでしょうか。このような学生の多くは、辞退の申し出に至るまで、悩みに悩んで決断をし、心が決まった状態で連絡をしているため、このタイミングでいくら手厚くフォローしても、内定辞退を覆すのは非常に難しいどころか、しつこく引き止めたせいでもっと遠ざかってしまうことすらあります。
ということは、突然辞退の連絡が来る前に、辞退の兆しを察知しておくことが重要なのです。では、辞退の兆しはどういったところに隠されているのでしょうか?以下に、辞退リスクのある学生の特徴と、そういった学生に対してするべきコミュニケーション方法を挙げていきたいと思います。
すぐに内定承諾した学生
内定を通知した際、すぐに承諾する学生と、そうでない学生がいます。
もちろん第一志望だったため即決して就職活動を終わらせる学生もいますが、内定承諾の重みは学生によって異なることを理解しておきましょう。「今選考に進めている会社は全て結果が出てから比較して決める」といった意図で、とりあえず内定は承諾しておく、という学生もいます。
すぐに内定承諾をした学生には、「併願していた企業の今後の進め方」も併せてヒアリングすることで、本当に入社する意思が固まっている状況なのかを確かめることができます。もしもまだ意思が固まっていない状況であれば、その理由に応じて、継続したフォローが必要となります。
OBOGネットワークの強い部活・サークルに所属している学生
例えば次のようなケース。「一度は内定承諾したものの、その後部活の先輩に誘われて、ある会社のリクルーターと面談。トントン拍子に話しが進み内定に至った。随分と悩んだが、本当に自分に合っているのはその会社ではないかと思いはじめ、憧れの先輩もいるし、結局そちらの会社へ入社することを決めた。」とくに体育会系の部活や、数十年の歴史があり上下関係のしっかりしたサークルで起こりがちです。
選考や面談の中で、大学時代に所属していた部活やサークルについてヒアリングしている企業は多いと思います。このケースのように、本人は内定承諾をして就職活動を終えたつもりでも、先輩や同期に影響され、しばらく会わないうちに考えが変わることはあり得るため、採用担当者は、部活やサークルでのエピソードに加え、「先輩や周りの同期が実際にどういった会社への就職を決めているのか」を聞いておき、定期的にケアする必要があります。
親の影響を受けやすい学生
「オヤカク」(※)という就活用語が有名ですが、親に反対されて辞退をする学生もいます。反対する親の特徴として、自分の子どもがやりたいことや将来の目標などといったポジティブな面ではなく、「待遇」「働き方」などにおいてネガティブな面がない会社に就職してほしいという思いをもつことがよくあります。
内定承諾をした時点で、「両親や家族の反応はどうだったか」を聞いておき、もし学生の両親がネガティブ面がないかを気にしているようであれば、安心させられる情報の提供をするなどの対応をしましょう。
※会社側が、内定承諾した学生に対し、親の承諾を得ているかを確認すること。または学生の親へ直接連絡をして承諾を得ること。
併願している企業の中に、採用力の高い会社がある学生
学生は、社員との接触回数が多いほど、またコミュニケーションの濃度が高いほど、志望度が高くなりがちです。過去に参加した他社のインターンシップを通して尊敬できる社員を見つけたり、自分の強みや弱みを的確にフィードバックしてくれた体験から、その会社への志望度が上がっている可能性もあります。「併願している他社とは、どういう出会いだったのか、どういったコミュニケーションをとっているのか」をヒアリングしておきましょう。
また、そのような会社と比較されたときに、コミュニケーションの回数や濃度で引けを取らないためにも、できるようであればインターンシップやアルバイトに誘ったり、現場の社員と交流できる機会を設けるなどの対応をすることをお勧めします。
承諾せずに長期間返答を保留している学生
言わずもがなですが、第一志望の企業であればすぐに内定承諾をするはず。それを長期間保留にしているということは、志望度が高くないので他の企業を探しているか、本命企業の選考結果がまだ出ていないことが考えられます。まずはその学生の就職活動の状況をこまめにチェックすることが重要です。
ただし、ここで注意したいのは、学生と企業は対等な関係であるべきことを意識することです。学生にとって、入社する会社を決めることは将来に関わる重要な決断であることは重々承知の上ですが、一緒に仕事をすることになるかもしれない相手ですから、お互いが誠意をもったやり取りができる状態を意識的に作ることが重要です。企業から学生へこまめに連絡をするだけでなく、例えば「一週間に一度就職活動の状況について報告の連絡を入れてもらう」などの約束事を作り、対等な関係性を築いていくと良いでしょう。
最後に
ここに挙げた例はほんの一例にすぎませんが、辞退を察知し、学生から申し出る前に対策をするヒントになれば幸いです。
当然、学生が新卒入社する企業は一社ですので、悩みに悩み抜いた結果内定を辞退することはあり得ることです。新卒採用活動のもう一つのゴールは、「この会社に出会えてよかった!」と思わせることではないでしょうか。そうすることで、長い目で見れば学生が自社のファンになってくれたり、後輩へのポジティブな口コミが広がったりと、採用ブランディングの形成にも繋がるでしょう。
母集団形成におすすめ

インターンや会社説明会の求人を無料掲載できる
- 導入企業1,500社 学生10万人以上の実績がある急成長メディア
- 3人に1人は東大、早慶、8割がGMARCH以上クラスと優秀な学生がほとんど
- メルマガやオファー送付など個別の集客プランも対応可能
おすすめの記事一覧

scoutコラム表示テストです~
続きを読む
てすと
続きを読む
てすとコラム 企業向け
続きを読む
テストコラム 企業向け
続きを読む
タグ追加テスト
続きを読む