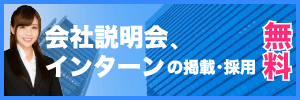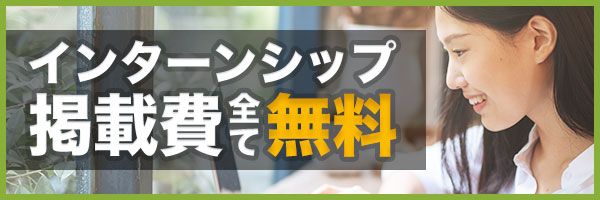新卒採用でのリクルーター活用例とポイント
新卒の学生を採用するのに、非常に便利なリクルーター。新たに導入しようとしている企業も増えていますが、経験がないと「リクルーターってどう使えばいいの?」と疑問に思ってしまうかもしれません。そこで今回は、リクルーターにまつわる基本知識をご紹介します。

- ・リクルーターとは
- ├エントリー数を増やすことが目的
- ├優秀な学生を見極める役割も
- └内定辞退を減らす
- ・リクルーターの仕事
- ├大学に足を運んでかかわりを持つ
- ├学生の就活相談に乗る
- └自社をアピールする
- ・リクルーターが上手く機能するポイント
- ├大学のスケジュールや学生の都合に合わせる
- ├リクルーターの環境を整える
- └ターゲット像を共有する
- ・最後に
リクルーターとは
そもそもリクルーターとは、どんなものなのでしょうか。
エントリー数を増やすことが目的
リクルーターの目的の一つは、自社にエントリーする学生を増やすことです。なるべくたくさんの母数を集めれば、多くの選択肢から採用する学生を吟味でき、より優秀な新入社員を獲得しやすくなります。リクルーターは自分が入社してからこれまでの話などをして、学生に「自分もここで働いてみたい」と思わせるのが仕事です。
優秀な学生を見極める役割も
リクルーターは学生と直接やりとりをするため、単に履歴書やESを送ってくる学生よりも「この人は優秀か」「自社の社風にあっているか」などを見極めやすくなります。会話の中でコミュニケーション能力を見定め、受け答えからどれほどスマートかを確認することができるんです。
エントリーしてきた学生全員に一律面接をするよりも、普段の会話や世間話の中で判断するので、「こんな学生なら採らなかったのに」という採用後のギャップも生まれにくいでしょう。
内定辞退を減らす
リクルーターが学生と企業の間に入ると、内定辞退がしにくくなります。学生側も、自分のために時間を割いて親身に相談に乗ってくれた先輩を裏切るわけにはいかないという心理が働くので、安易な気持ちで選考を進めたり、内定を蹴ったりしなくなるのです。
せっかく採用を決めた学生に入社を断られたら、その分の採用コストが水の泡。それを予防する意味でも、リクルーターは活躍しています。
リクルーターの仕事
実際に、リクルーターはどんな仕事をしているのでしょうか。
大学に足を運んでかかわりを持つ
リクルーターの学生アプローチ方法としては、自身の母校に足を運ぶことが多いでしょう。学生時代に所属していたゼミやサークルに行き、今自分がどんなことをしているかなどを話して、学生の興味を引きます。もともと同じコミュニティに属していたという事実があるので、完全な他人がリクルートするよりも学生の警戒感が薄まります。
他には、大学時代にお世話になった教授に、マッチングしそうな学生を紹介してもらうこともあります。また、ESを読んでこれはと思う学生がいれば、個別に連絡を取るという方法もあるのです。
学生の就活相談に乗る
OB、OGの立場として、学生の就活にまつわる全般的な相談にのることも仕事のうち。無理やり自社の選考を受けさせようとすると学生は拒否反応が出てしまうので、選考中の他の企業についてや、インターンシップについてなど、幅広く話を聞きます。
そうしているうちに「この人には頼れる」という信頼関係が築かれ、「○○さんの△△という特徴は、うちにあっていると思うよ」などとさりげなく進め、「この人が言うなら受けてみよう」と思わせます。
自社をアピールする
就活の相談に乗る中で、上手く自社をアピールする必要もあります。企業理念やキャリア形成、福利厚生など全体の話もそうですが、基本的な部分は、パンフレットや採用サイトを見れば大抵のっています。だからこそ、個人的に達成感のあった仕事や成長した点などを話すと良いでしょう。
「社会人一年目でこういう仕事をして、それがこれに繋がって、こういうプロジェクトに参加できた。この経験で自分の○○力が伸びたと思う」など、なるべく具体的に語るのがベスト。学生が、「この会社に入ったらどうなるだろう」と考えた時に、そこにいる自分を想像できるようにしましょう。
リクルーターが上手く機能するポイント
せっかくリクルーターを導入するなら、きちんと機能させたいですよね。そのためのコツは、3つあります。
大学のスケジュールや学生の都合に合わせる
大学生のとって就活は大切ですが、それだけをしているわけではありません。授業に出たりテストを受けたりする必要もありますし、サークルを頑張っている人もいれば、バイトのシフトをたくさん入れている人もいます。そうした個人のスケジュールに、なるべくよりそうと良いでしょう。
学生からすると、社会人として働いているリクルーターから提案された日程を断るのは、少し勇気がいること。それが何度も続くと「申し訳ないからもう連絡しないでおこう」となってしまいます。リクルーター自身の仕事との兼ね合いを考えながら、学生のスケジュールを反映した日程調整が大切です。
リクルーターの環境を整える
通常業務に加えてリクルーターをやると、どうしてもいつもより負担が大きくなります。また学生のスケジュールにあわせるということも非常に難しくなってくるので、仕事量を見直してみてください。
リクルーターの業務は、一時的に発生するもの。だからこそその期間は同じ部署のメンバーにフォローしてもらいながら、リクルートに集中できるよう環境を整えましょう。また、上司から他の社員にしっかりと「彼/彼女にはリクルーターとしてこういう業務をしてもらう、そのため負担をシェアしたい」という旨を話さないと、周りから見ていて何をするかわからないので「あの人はサボっている」なんて思われたりしてしまいます。
ターゲット像を共有する
人事部の考える「自社にぴったりの学生」と、リクルータの考える「自社にぴったりの学生」がずれていると、いざ面接となったときに「なぜこんな学生をリクルートしたのか」となってしまいます。まずは人事部で理想の学生像を練り上げて、それを芯から理解するまでリクルーターに共有をしましょう。
最後に
リクルーターは、上手く使えば優主な学生を獲得する非常に便利な役割です。名前だけのリクルーターではなく、しっかりと選考に役立つように、これらのポイントを忘れないでください。
母集団形成におすすめ

インターンや会社説明会の求人を無料掲載できる
- 導入企業1,500社 学生10万人以上の実績がある急成長メディア
- 3人に1人は東大、早慶、8割がGMARCH以上クラスと優秀な学生がほとんど
- メルマガやオファー送付など個別の集客プランも対応可能
おすすめの記事一覧

scoutコラム表示テストです~
続きを読む
てすと
続きを読む
てすとコラム 企業向け
続きを読む
テストコラム 企業向け
続きを読む
タグ追加テスト
続きを読む